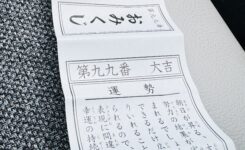【防災士】という資格を知っているでしょうか?
近年、日本でも一年を通して必ずと言っていいほど何処かで何かの災害が起きています。
もちろんこの【災害】には、地震や台風などの【自然災害】や、テロや交通事故などの【人的災害】も含まれるのですが、今後身近に起こりうる可能性が決して低くないと思い、今回【防災士】の資格取得に向けて講習会などを受講してきました。
まず、【防災士】ってどんな資格なの?って事で、色々な方がそれぞれのブログ等で丁寧に説明されているのでそちらを参考にした方がいいと思いますが、はっきりしている事は弊社にとっては、この資格があるからと言って仕事の受注や売上が増える様な事はないという事です。
なので周りの人に取得にチャレンジする事を伝えても、『ふぅ〜ん』程度の返答です。資格自体が【民間資格】で【国家資格】ではないので当然かもしれません。では、なぜその様な仕事に活かせない資格を取得したのかと言うと自分自身への【安心感】のためだと思います。
実際に、2日間の講習を受けた後にテストをして合格者が【防災士】となる事が出来るのですが、突然の【災害】が起こった時に講習で受講した内容を100%発揮出来るかと言うと全く自信がありません。多分、ほとんどの人がそうだと思います。
ただ、今後必ず起こる【災害】に対して、なんの知識も無いままでその時を迎えるよりは少しでも予備知識と心の準備ができていた方がいいだろうと言う【安心感】のためです。
もちろん、【防災士】全てが同じ様な意見では無いですので、あくまでも個人的意見です。
さて、ではどの様にして【防災士】の資格を取得できるのかですが、これも既にいろんな方が説明しているのですが任せっきりもどうかと思うのでザックリと説明します。
まず、【防災士】になるには2日間の講習受講をした後に試験をして80%以上の合格で【防災士】の資格取得ができます。これを行なっているのが【日本防災士機構】という所です。
それぞれの場所で行われている様ですが、私は北海道ですし海を渡って受講する訳にもいかないので札幌会場での申し込みとなります。幸い、会社も札幌市ですし特に気にもしないで申し込みをしました。ただ、受講料が高いのが難点です。確か60,000円弱の費用が掛かった記憶があります。この時から自分の中では、講習を受講すればほぼ100%合格にしてくれる類の資格なんだろうと思い込んでいました。
受講申し込み後、程なくしてから教材が届きました。
それがこれです。
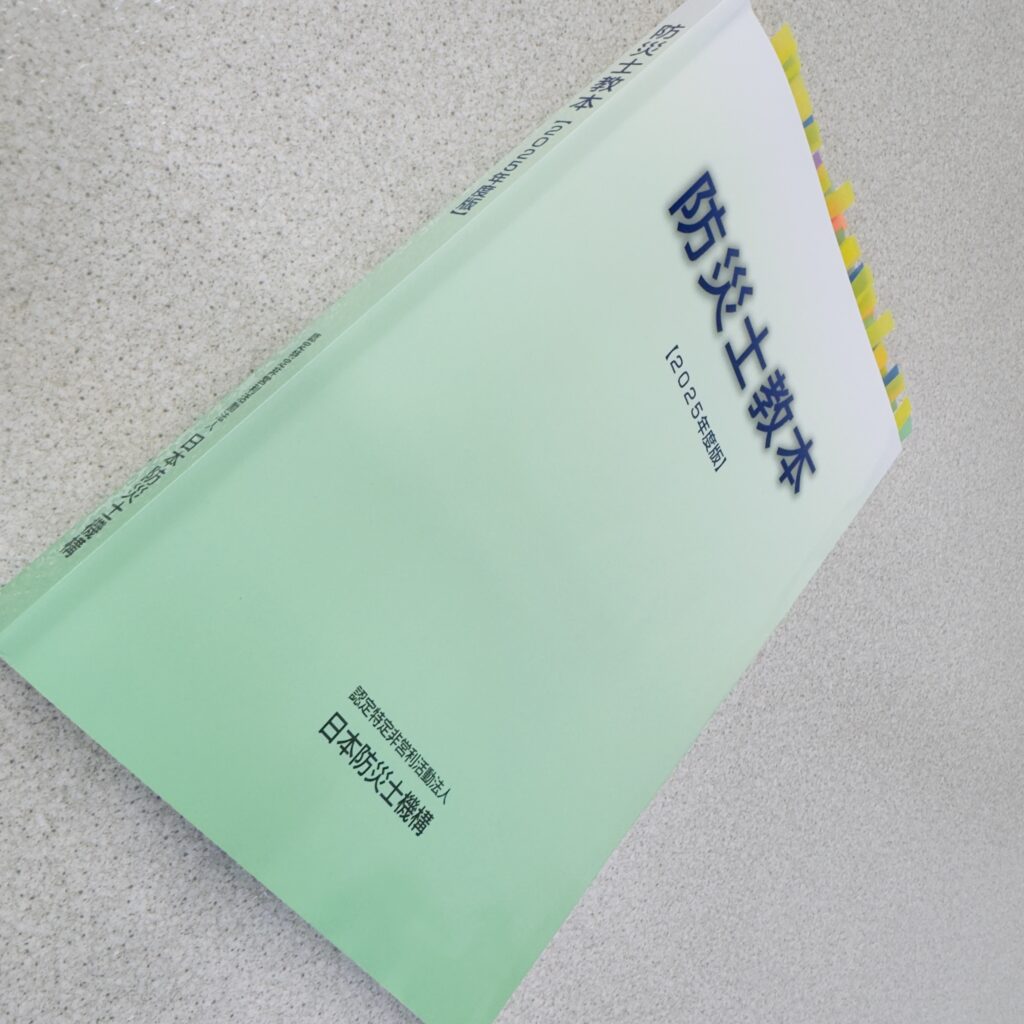
400ページ弱のページ数があり、これを受講日までに熟読してレポートの提出をしなければいけないとの事。
数年前から老眼が始まり、小さな文字などを大量に読むとすごく目が疲れる自分にとっては、拷問に近い内容です。でも、やらなければいけないのでまず提出用のレポート用紙の問題を見ながら答えの場所にマーカーで色塗りをしてページの箇所に付箋を貼っていきます。そこまで出来ればあとは付箋をした場所を書き写していくだけなので毎日寝る前に少しづつ穴埋めをしていきます。それでも前日まで掛かってしまったのですが。
さて、仕事をしながらなんとかレポートも間に合いいよいよ受講当日です。会場には30人前後くらいの人達が集まっていて、聞こえてくる会話の中には『札幌まで移動で3時間掛かった』や『どこのホテルに泊まっている?』などの会話や会社で受講に来ているのか、仕事の話をしている人達もいました。
受講が始まって2時間位毎に講師が変わってそれぞれ違った内容の話をします。一番最初は気象予報士でもある、菅井貴子さん。この方、声は聞いたことあるなと思ったら、テレビでお天気やっている人だったんです。自宅では録画したものやNetflixしか見ていないので、気が付けなかったけどもとても分かりやすくて眠くならない話をしてくれました。お天気や災害に関する書籍を出しているらしく、ちょっと気にもなっています。
1日目の最終講義は、災害避難場所をカードゲームの様に学んでいける【避難所運営ゲーム北海道版(Doハグ)】の実践です。7人1チームに分かれて、避難場所に様々な事情を持った人達が避難してきた場合に、誰をどこに配置するかなどをカードでゲーム形式で行う模擬体験の様なものです。この【Doハグ】の説明や段取りは実際の【防災士】の方々が来てくれて進めてくれたのですが、正直な話をすると【ちょっと段取り悪くない?】【何をどうすれば良いのか要点が伝わらない】など、【実際の災害時は大丈夫なの?】と思う様な場面もしばしば。でも、始まってしまえば結構楽しく、若い子供達を対象にしていくのなら十分目的を果たせるゲームだなと思いました。
その様な事をしながら、1日目が終了です。ここで『ん?』と思った事が。あの分厚い教本を使っていない気がする。そんな疑問を持ちながら2日目開始です。
2日目の最終には試験があります。全30問の出題で24問以上正解で合格です。80%以上の正解なので結構厳しい合否率だと思います。
気になって1日目が終わって車を停めているコインパーキングで、【防災士】の合格率を調べてみたら2024年度で91.8%で約9%の人が不合格になっている事を知りました。正直、2日間の講習で60,000円近くの受講料(その他受験料や認定料も含まれる)を払っているのに不合格の可能性もあるのです。
1日目は教本を使う事がほとんど無かったのですが、2日目も同様です。ここで思ったのが、『試験問題ってどこから出るの?この2日間は試験問題と関係なかったの?』って事です。
そんな疑問を持ちながら、最終時間の試験開始です。試験開始までは『もしかしたら教本見ながらの試験OKかな』と期待もしていたのですが、そんな事もなくガッツリと本気の試験でした。
試験の内容は一応は、提出したレポートの内容に沿っているのですが、教本には記載されているがレポートの範囲では無いところからも出題されていて30問中6問しか間違う事が出来ないとなると、結構不安が残る結果となります。
試験が終わり。最初にした事は【不合格だったらどうなる?】を検索する事でした。一番最初に書いた通りに100%合格させて貰える受講だと思っていたので、ほんの少しも不合格の事など考えてもいませんでした。
前日と同じようにコインパーキングに停車した【アリア B9 e-4ORCE】の車内で、スマホ片手に検索開始です。調べてみると結構『不合格だった』って人がいる事にビックリです。でも約1割の人が不合格になっているのであれば当然かもしれません。で、そんな人達が気になっていたのが『再試験ってあるの?』でした。まさに自分もそこが知りたくて調べていたのでちょうど良かってです。結論から言いますと、再試験は無料で実施されているとの事でした。ただ、地域によっていつどこで再試験が行われるかはバラバラらしくまずは、合否結果を待つしか無いのが現状です。
と、ここまでは10月14日に書いた記事なのですが、その後自宅に合否結果が郵送されてきました。
結果はなんとか【合格】です。正直、いくら無料とはいえ、また試験の為に教本を読み返すのはちょっと苦痛だったので良かったです。でも、他の方のブログなどを見ると全問正解で合格された方は合格通知に【全問正解】と記載されているみたいなので、私は多分80%ギリギリでの合格だったんじゃ無いかと思っています。
この様に【防災士】になるには、2日間の時間を取られた上、落ちる可能性のある試験を受けるのに60,000円近い受講料を支払わなければ取得できない【民間資格】です。それでも【今後必ず起こり得る災害】に対する【安心感】と【予備知識】の為には受講して無駄ではなかったと思っています。今後はせっかく取得できた資格なので、今回のこの記事の様に少しでも他の人に興味を持って貰えるような発信が出来れば【防災士】でなくても同じような【安心感】と【予備知識】を持って貰えるかなとも思っています。
最後に、【防災士】になるには年齢や性別などの条件はありませんが、①今回受けた講習を受講する ②防災士資格取得試験に合格する ③救急救命講習を受講する(または受講後5年以内である)が、必要となります。この3点を全てクリアすると【日本防災士機構】に申請する事ができて【防災士認定証】が発行されます。